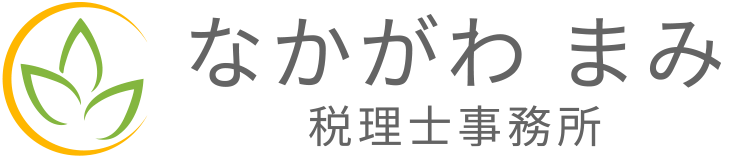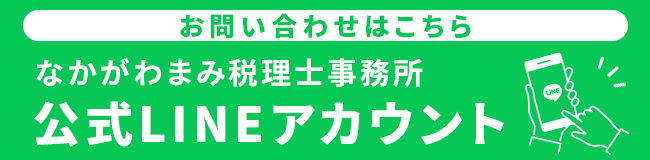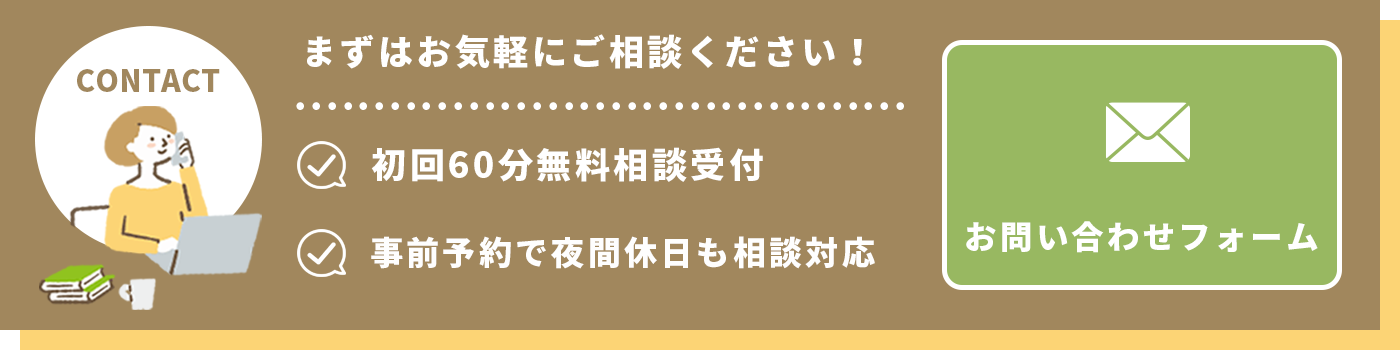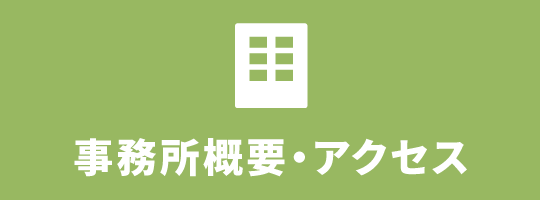このページの目次
古物商向け:取引記録と税務処理のポイント ~インボイス制度にも注意~
本記事では、古物商に求められる記録義務と税務上の注意点、そして2023年10月から始まった「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」について詳しく解説します。
古物商の取引記録義務
古物営業法により、古物商は取引の際に以下の情報を古物台帳に記録し、3年間保存する義務があります。
- 取引の年月日
- 古物の品目および数量
- 古物の特徴(メーカー名、ブランド名、色、材質、シリアルナンバーなど)
- 取引相手の住所、氏名、職業、年齢
- 取引相手の身分確認方法
なお、一部物品を除き、取引の総額が1万円未満の場合には記録義務が免除されます。
税務上のポイントとインボイス制度
◆ インボイス制度とは?
2023年10月より導入された「適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)」は、消費税の仕入税額控除を受けるために、登録された事業者(適格請求書発行事業者)からのインボイス(適格請求書)を保存する必要がある制度です。
◆ 古物商特有の注意点
① 一般消費者からの仕入れが多い
- 古物商は一般個人からの買取が主であることが多く、仕入先が適格請求書発行事業者でないケースがほとんどです。
- この場合、インボイスは交付されず、仕入税額控除ができません。
② 免税事業者からの仕入れも対象外
- 例えば、フリマアプリやオークションなどでの仕入れで、出品者が免税事業者である場合、その取引もインボイスの対象外となります。
③ 古物台帳をしっかり残せば、一般消費者からの仕入も仕入税額控除できます!
- 一定の条件を満たせば、帳簿記載をもってインボイスの代替が認められる「帳簿方式(古物商特例)」があります。
- 例えば、古物商が適格請求書発行事業者でない者(一般個人など)から中古品を仕入れる場合、所定の事項を帳簿に記載することで、仕入税額控除が認められる特例があります。
【帳簿記載が必要な主な項目】
- 相手方の氏名・住所(または氏名のみ)
- 取引年月日
- 取引の内容(古物名など)
- 支払対価の額
- 適格請求書発行事業者でないからの仕入れである旨の記載
※この帳簿記載をもって、インボイスの保存に代えることができます。
まとめ
古物商の皆さまは、日々の取引記録の整備に加え、インボイス制度への理解と対応が求められます。とくに仕入れの多くが非インボイス対応取引となる古物商業界では、帳簿保存特例の活用が重要なキーワードです。
「どの取引で帳簿保存特例が使えるのか?」「インボイス発行事業者になるべきか?」など、ご不明な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
お気軽にご相談ください
税金や経理のことだけでなく、
「ちょっとお金のことで不安がある」
「経営の今後について誰かに相談したい」
そんな時に、まず思い浮かべてもらえる税理士でありたいと考えています。
「こんなこと聞いていいのかな?」と思うようなことでも、遠慮なくご相談ください。
オンライン面談にも対応していますので、全国どこからでもお気軽にご連絡いただけます。
▼お問い合わせはLINEから
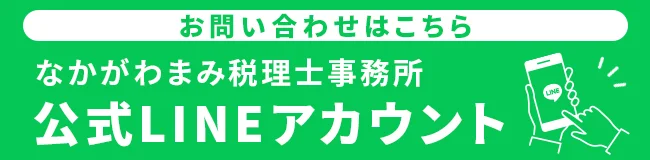

当事務所では、クラウド会計を活用した効率的な記帳や、日々の経営に寄り添う節税提案を行い、お客様の大切なお金をしっかり守ります。税務調査の際にも、お客様の立場に立ってしっかり対応いたします。
兵庫県西宮市を拠点に、JR西宮駅・阪神西宮駅周辺をはじめ、夙川、甲子園、苦楽園口など、西宮市内のさまざまな地域で事業を営む皆さまをサポートしております。大阪市や兵庫県内はもちろん、全国からのご相談にも対応しています。
LINEからのお問い合わせも受け付けており、事前にご予約をいただければ時間外のご相談も可能です。お困りの際は、どうぞお気軽にご連絡ください。