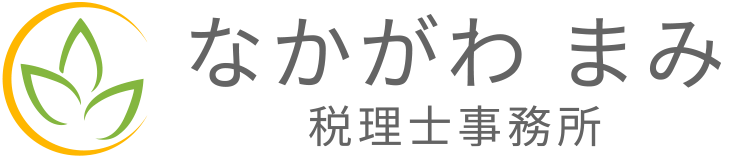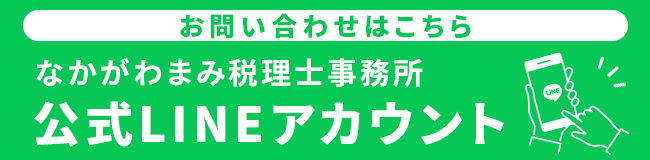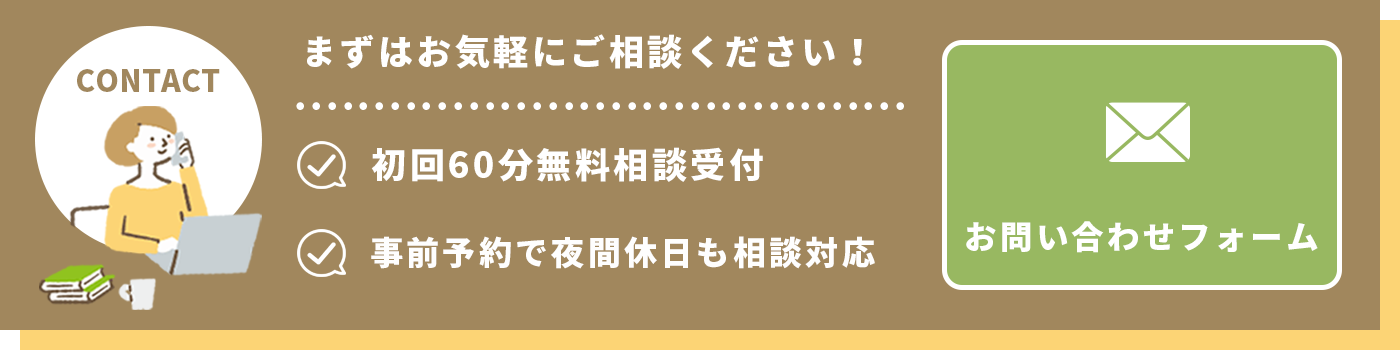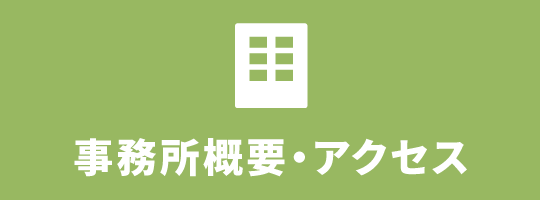このページの目次
インボイス制度ってなんだ??
インボイス制度は2023年10月に開始した制度です。
詳細は割愛しますが、一言でいうと、売上1000万円以下の免税事業者からの益税が問題視され、免税事業者からも消費税を徴収するための制度です。
これまで、事業者が仕入先に支払った経費について、相手が免税事業者であっても、自身が納付する消費税から控除することができました。
しかし、インボイス制度が始まってからは、消費税を控除するには、相手がインボイス登録をしている課税事業者である必要があります。
仕入先・外注先が免税事業者の場合には、相手が消費税を納税しない代わりに、支払ったこちら側が代わりに消費税を負担することになってしまいました。
インボイス制度でなにが困るの?
インボイス制度で困ることは、①金銭的な負担と、②事務的な負担の2種類があります。
① 金銭的な負担
これまで免税事業者だった事業者が、得意先の要請をうけてインボイス登録することになり、消費税を負担することになった
→ これまで免税事業者だった方が消費税負担することになると、納税により資金繰りに大きな影響がでます。これまでの利益を確保するためには、売上単価の値上げ交渉や経費の見直しなどを講じる必要があります。
自分は課税事業者だが、仕入先・外注先が免税事業者のため、自身の納付する消費税が増えてしまう
→ 仕入先や外注先が免税事業者の場合、相手が消費税を納付しないため、その分こちらが消費税を負担することになります。そのため、仕入先との金額交渉や、ひいては別の取引先に変更するなどを検討する必要があります。
② 事務的な負担
ひとつひとつの支払いごとに、請求書・領収書にインボイス登録番号があるか確認しないといけない
→ これはかなりの手間だと思います。いままで領収書保存だけでOKだったのが、領収書にインボイス登録番号があるかどうか、を確認して記帳しないといけません。領収書・レシートの形式によって、登録番号が記載されている場所も違うため、毎回毎回地味にストレスです。。。
各会計ソフトから出ている領収書撮影用のカメラアプリで撮影すると、インボイス番号番号の有無も自動判定してくれるため、うまくアプリを利用して、効率化しましょう。
インボイス導入により消費税の計算方法の選択肢がさらに広がり、どれが得かわからない
→ インボイス導入により、計算方法が「原則課税」「簡易課税」「2割特例」と計算方法の選択肢が増え、さらに、どれを選ぶかによって納税額に大きな差が出るため、どの計算方法を選ぶのか、を納税者がシミュレーションする必要があります。
とりあえずインボイス登録をしたが、消費税申告ってどうすればいいのか?というあなたへ
これまで、所得税についてはご自身で申告されていた免税事業者も、消費税は専門知識が必要であるため、税理士を探される方が増えてきたように思います。
先の述べたように、ひとつひとつの領収書を確認する必要があるので、クラウド会計やITツールに頼らずに対応しようとすると、帳簿入力だけでかなりの時間がかかり、本業に支障がでることにもなりかねません。
クラウド会計ソフトの便利機能を使ったり、消費税に強い税理士に相談し、ある程度割り切ってよいライン・特に注意すべきポイントをおさえ、できるだけ効率的に帳簿入力を行っていくことが大切です。
インボイス制度導入後、消費税はさらに複雑になりました。
実は、もっとも申告誤りや税理士への賠償が多い税金が消費税です。
「原則課税」「簡易課税」「2割特例」「1億&1万基準」「免税事業者8割→5割控除」「居住用賃貸不動産の特例」などなど、複雑で落とし穴が多い税金です。
また、法人税や所得税と異なり、自分で申告方法を選択することができ、それぞれの計算方法により税額にはかなりの差があります。
クラウド会計を上手に利用し、消費税が得意な税理士に相談して、自分にとって一番お得な計算方法をえらびましょう。
私は税理士試験のうち「消費税法」に合格・取得しています。
奥の深いといわれる消費税の知識にはかなり自信があります!
(ちなみに、消費税と同じくらい奥が深いといわれる「相続税」はあまり詳しくありません…笑)