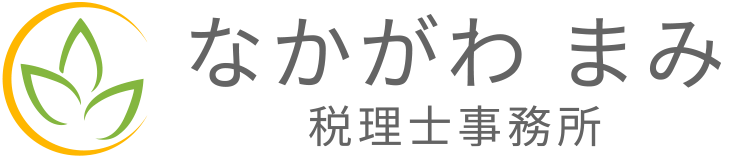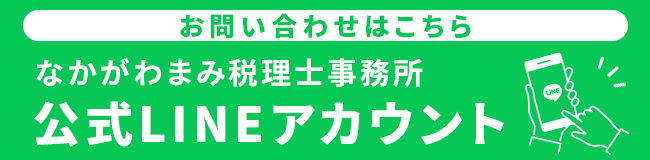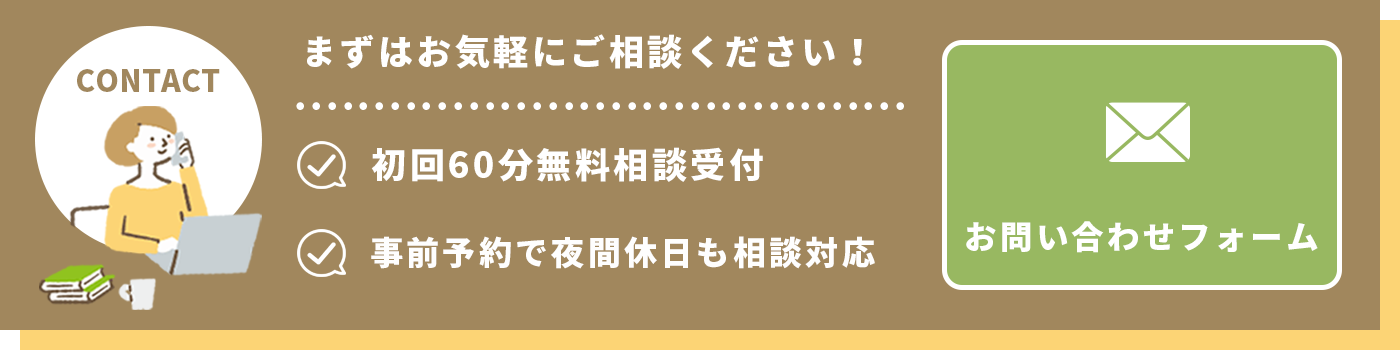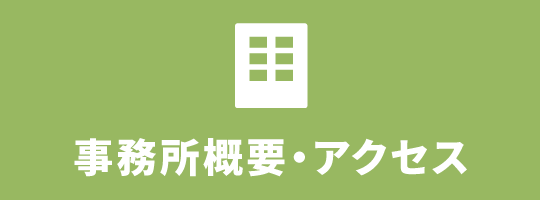最終更新日
西宮市で新たに事業を始められた方、法人設立をされた方へ。
「税理士に相談したいけど、どんな人がいいのかわからない」
「分からないことだらけなので、流れ作業ではなく、丁寧に対応してほしい」――
世の中に会社や事業はたくさんあれど、その方にとっては起業はとても不安な第一歩です。
そんな初めての不安や疑問に、西宮の女性税理士がやさしく寄り添い、丁寧にサポートいたします。
弊所はそれぞれのお客様に寄り添った丁寧な対応ができるように、対応するお客様の数を絞っています。
絶対「ほったらかし」にしません。
このページの目次
当事務所が選ばれる理由
- 30代の代表女性税理士が直接対応
相談しやすさ・説明のわかりやすさ・きめ細やかなサポートが強みです。すべて代表税理士が対応しますので、経験の少ないスタッフが担当したり、担当替えがあることはありません。 - 説明がわかりやすい
ご契約いただいた理由をお聞きすると「とにかく説明がわかりやすかった」と言っていただくことが多いです。「税理士任せ」ではなく、起業されたご自身が会社の税金やお金のことをご理解いただくことが大切だと思っていますので、専門用語を使わず、わかりやすく説明します。 - 西宮密着でフットワークが軽い
地元ならではの迅速な対応。ご希望に応じて訪問やオンライン相談も可能です。 - オンライン相談・土日対応もOK(要予約)
忙しい方や遠方の方もご利用いただけます。ご都合に合わせて柔軟にご対応します。
相談からご契約までの流れ
- お問い合わせ
お問い合わせフォームまたはLINEからご連絡ください。 - 面談(対面またはオンライン)
ご希望の方法で面談。ご相談内容やご要望をじっくりお伺いします(無理に顧問契約を進めることは絶対ありませんのでご安心ください) - お見積もり・ご提案
ご要望に合わせたサービス内容・料金をご提案します。 - ご契約・サポート開始
ご納得いただけましたらご契約。以降も代表の女性税理士が責任をもってサポートします。
相談事例(よくあるご相談)
- 西宮で開業したばかりの40代経営者さまからのご相談
「経理や税金のことが全く分からない」「同年代同士で相談したい」 - ご自身で申告されていた個人事業主さま
「節税や経費計上のコツを知りたい」「インボイス制度の対応が不安」 - 西宮でママ起業予定
「個人事業主がよいのか、法人がよいのか、違いやメリットデメリットが知りたい」
新たに開業・法人設立したが、開業手続きや申告の方法がわからない

新たに事業を始めたり、法人を設立したときは、開業前から様々な準備費用がかかります。
「なにが経費になるのか?」「領収書はどう保存したらいいのか?」「会計システムはなにを使おうか?」など様々なお金のハテナ?が生まれます。
本業が忙しくて、ついつい帳簿入力や税金関係の手続きは後回しになりがちですが、開業後すぐに申請しないと受けられない、税制上の優遇措置(青色申告控除や専従者給与など)もあります。
決算前に「そろそろ申告のこと考えないと・・・」となってから申告の依頼をいただいたお客さんのなかには、今年は届出期限が過ぎていて優遇税制が受けられない、というもったいない事例も少なくありません。
「1年にどんな手続きや税金の支払いがあるのか」「どんな会計ソフトがあるのか」など、起業したては分からないことだけ。基本的なことから丁寧にわかりやすく説明します。
とりあえずインボイス登録をしたが、どうすればよいのかわからない
2023年10月に開始したインボイス制度は、なかなか複雑な制度です。
西宮の事業者様からも、「これまで売上1000万円以下で消費税免税事業者だったけど、クライアントの要望でインボイスをすることなった。どうしたらいいかわからない」とのご相談をよくいただきます。
これまで、ある程度ご自身で申告されていた方も、消費税の帳簿入力はかなりの専門知識が必要となり、税理士を探される方が増えてきたように思います。
👉インボイス制度について詳しくはこちら
クラウド会計ソフトの便利機能を使ったり、消費税に強い税理士に相談し、できるだけ効率的に帳簿入力を行っていくことが大切です。
今まで自分で申告してきたが、事業が大きくなり、このままでよいか不安
国税庁の「確定申告書等作成コーナー」は、毎年どんどん分かりやすくなっていますし、今はネットやYoutubeで税理士も多数発信していますので、ご自身で調べながら申告されているかたも増えてきました。
正直、個人事業主で収支の集計が簡単な事業であれば、十分申告できると思いますし、特に規模の小さい方は明らかな誤りがない限り、税務調査に来る可能性も低いと思うので、ご自身で申告されるのでも十分だと思います。(税理士としてはあまり言いたくないですが…笑。)
西宮市内でも、個人事業主の方がご自身で申告書を作成されているケースを多く拝見しますが、実は「あと一歩で節税できたのに…」というもったいない事例が少なくありません。これまでの申告書を拝見して、わかりやすく丁寧にアドバイスいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。
頑張って売上をあげたのに、融資が下りなかった
融資をするときに、金融機関から直近2年分の確定申告書の提出を求められると思いますが、銀行は確定申告書・決算書をみて、会社の財政状態・返済能力を見極めています。
残念なことに、金融機関は大量の融資審査をしなくてはならないので、「確定申告書をみても財政状態がわからなかったので、詳しく教えて!」とは言ってくれません。申告書から読み取れない場合は、そのまま不安要素としてネガティブとして放置されてしまうのです。
決算書のなかでも貸借対照表が重視されますし、法人であれば申告書に添付する「勘定科目内訳書」のなかで、滞留債権や不良在庫はないか?返済能力はないか?を見られます。
申告書は税金計算のためだけに作成しているものと思いがちですが、将来的に融資を申し込むことも想定し、申告書・決算書で事業の健全性がアピールすることも念頭に置く必要があります。
「税務申告してくれる税理士」と、「将来の融資のことも考えて決算書を作成してくれる税理士」では、将来の融資の審査や利率に影響してきます。
収支や損益分岐を自分で管理できるようになりたい
経営者の皆さんは、集客や売上についていつも頭を悩まされていると思いますので、大多数の方は、「今年の売上がいくらになるか?」をお聞きすると、みなさん即答できます。
ただ、「この事業でいくら儲けたいですか?」「来年は自分の手元にいくら残したいですか?」「固定費はいくらで、黒字化するにはいくらの売上が必要ですか?」という経費・利益関連の問いには、実はあまり具体的にイメージできていない方も多くいらっしゃいます。
売上はあがっているが、実は事業資金は増えておらず、社長さんの貯金を取り崩している状態という方はかなり多くいます。
事業を行ううえで、売上だけではなく、「収支を見える化し」「資金繰りを予測する」ことが、事業を成長させ、成功させる秘訣です。
クラウド会計で効率的に記帳し、自分の事業の実態を把握して、事業を成長させていきましょう。なかがわまみ税理士事務所は自計化支援専門の事務所です。経理が苦手でも3ヶ月で自分で記帳できるようにサポートします。
はじめて税理士を探すときのポイント
1 自分が税理士に何をのぞんでいるかを明確にする
税理士とのミスマッチを防ぐには、税理士にお願いする前に、自分がなぜ税理士にお願いしようと思ったのかを考えてみましょう。
例)
事業を始めて税金のことが不安
→ 自分と年齢が近く気軽に話せる税理士、面談回数やチャット相談に制限を設けていない顧問税理士を探しましょう。(顧問税理士の中には、プランによって面談回数や相談回数に制限を設けているプランが多いので、設立・創業したてのかたには、あまりお勧めしません。)
税理士丸投げではなくできるだけ自分で記帳し、試算表を理解するようになりたい
→ 自計化支援が得意、わからないことでも粘り強く教えてくれる税理士を探しましょう。
2 税理士の本当の「得意分野」を知る方法
税理士は数多くいますが、それぞれ得意分野が異なります。
HPに得意分野以外のサービスも書いてありますので、HPを見るだけではなかなか見抜きにくいです。
契約する前の面談で「あえて得意分野や強みを一つあげるとすればどういうことですか?」とぜひ聞いてみてください。
3 気軽に相談できるか、わかるまで遠慮せず聞けるか、一度話してみる
税理士は今後長くお付き合いする大切なパートナーです。
「同世代の税理士に相談したい」「話しやすい雰囲気がいい」「専門用語を使わずわかりやすく説明してほしい」――そんなご希望も、西宮のなかがわまみ事務所なら大歓迎です。
税理士は今後末永くお付き合いする相手ですので、気軽に話せるか、わからないときは正直に「わからない」といえるか、という相性は大切です。
まずはお気軽にご相談ください(無理に顧問契約をお願いすることは絶対にしません。しなさ過ぎて拍子抜けされることが多いくらいです)
西宮で税理士をお探しの方
ぜひご相談ください。
西宮市内・近隣地域の皆さまからのお問い合わせをお待ちしております。